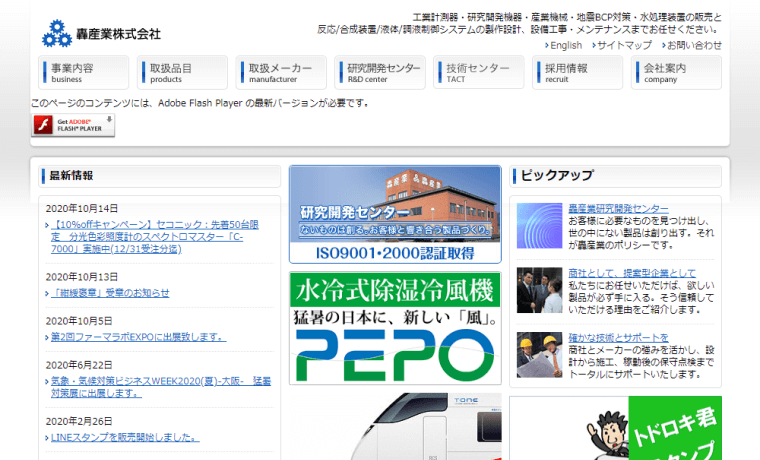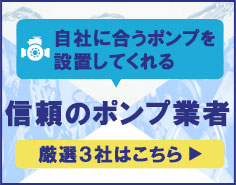公開日: |更新日:
ドライ運転(空運転)
設備故障トラブルのひとつとして「ポンプのトラブル」があります。このようなポンプのトラブルが発生してしまうと、より大きなトラブルにつながってしまう可能性があり、さまざまなロスが発生したり、点検・修理などに多大なコストや労力が必要になる場合があります。
このような状態を防ぐためには、ポンプトラブルの原因を知り、予防に務めることが大切。この記事では、「ドライ運転(空運転)」の原因や解決方法について紹介していきますので、チェックしておきましょう。
ドライ運転(空運転)の原因
まずはじめに、空運転とも呼ばれる「ドライ運転」が発生する原因について知っておきましょう。ドライ運転は、ポンプの内部や吸込み配管が液体で満たされていない状態(空気が入った状態)でポンプを作動させることが原因です。
ポンプを作動させる場合には、通常内部に液体が入った状態にしておく必要があります。空気が入った状態で運転させてしまうと、内部に摩擦が発生するためにペアリングやスピンドルなどが焼損・破損してします可能性がありますので、ドライ運転の状態を解消する必要があります。
ドライ運転(空運転)の解決法は?
上記の通り、ドライ運転が発生した状態ではポンプが破損してしまう可能性があるため、しっかりと対策を行っておきましょう。ドライ運転の対策を行う場合には、「タンクに対するポンプ軸の高さ」がポイントとなってきます。
ここでは、「ポンプ軸がタンク液面より下にある場合」と「ポンプ軸がタンク液面より上にある場合」の2パターンに分けてご紹介しますので、あらかじめチェックしておいてください。
ポンプ軸がタンク液面より下にある場合
まず、ポンプ軸がタンク液面よりも下にある場合についてですが、このケースではケーシング内に自然に液体が入っていくことから、ドライ運転のリスクは高くないといえます。ただし、この状態でドライ運転が発生してしまった場合には、エア抜きを行う必要があります。
エア抜きの手順は、まずタンク内に対して液体を十分に充填し、吸い込み側の仕切りバルブをしっかりと開きます。その後、エア抜きバルブを開いて液体が出てくるまでエアを除去します。このような手順でしっかりとエア抜きを行います。
ポンプ軸がタンク液面より上にある場合
また、ポンプ面がタンク液面よりも上にある場合については、ドライ運転の状態になりやすいために特に注意が必要となってきます。このことから、ドライ運転を発生させないために押さえておきたいポイントを2点ご紹介しますのでチェックしてきましょう。
呼び水やエア抜きを確実に行う
ドライ運転を防ぐためには、「呼び水・エア抜きをしっかりと行っておく」という点が大切になってきます。この場合の手順としては、まず呼び水によってポンプと吸込み感を液体で満たします。その後、エア抜きを行ってエア抜きバルブから液体が出るのを確認します。
ポンプ停止時の液体逆流を防止する
また、動力を停止した場合には、タンクに向かって液体が配管から逆流してしまうことがあるいう点にも注意が必要です。もし液体が逆流してしまった場合には、ドライ運転を防ぐために上記で説明した呼び水やエア抜きを毎回行う必要があります。このことから、逆流を防ぐためにもチェックバルブやフートバルブを利用しましょう。
なんでも相談できるポンプ業者は?
こちらの記事では、バルブのトラブルのひとつ「ドライ運転(空運転)」について紹介してきました。
バルブのトラブルが起きてしまった場合、その状態を放置するとより大きなトラブルに発展しかねません。このことからも、トラブルを解消するためには、確かな対処を行ってくれる業者に依頼することが大切です。しっかりと現場を見て、状況に応じてさまざまな提案を行ってくれる業者を見つけてください。
自社に合うポンプを設置してくれる信頼のポンプ業者・商社
●公式HP内に保有資格やポンプメーカーの種類が明記されている
●施工・設置までをワンストップで対応可能である
以上の基準でおすすめ業者・商社を選定いたしました。(2020年12月調査時点)
どのポンプ業者・商社も知識・技術・経験が豊富なので、自社に合う業者・商社がきっと見つかります。
用意できる?
に応えてほしい
100社以上のメーカーに対応しており、有名な商品から特殊な商品まで自社に合ったポンプを幅広く提案することが可能。
同じ型のポンプが無い場合でも、現場出身の営業担当が直に対応することでスムーズな代替案・代替製品の案内が可能。
アフターサポート
に応えてほしい
1934年の創業で、86年もの社歴を持つ同社。創業以来培ったノウハウと知識で、社員一人ひとりの質の高い提案が可能。
環境システム事業と菅工機材事業を同時に提供することができる専門商社でもあり、建物トータルのメンテナンスが可能。
総合的な構築
に応えてほしい
全国に44カ所の営業拠点があり、仕入れから販売まで行うことから、地域に特化したスピーディーな対応が可能。
現場に入り込む販売部門と様々な製品を用意できる技術センターの連携で、必要なものを必要な分だけ供給することが可能。